【第871回】 坐技呼吸法の進化
呼吸法を重視しながら技と体を鍛えている。これまでは、立ち技での片手取呼吸法が中心で、次に諸手取呼吸法をやっていた。道場稽古の前と後にやるようにしていた。はじめの内は、只やりたくてやっていたが、その内、やるべき課題や目標をもってやることにしていた。例えば、曲がらない手をつくる、手の親指を支点として手の平を返す等々である。
何故、呼吸法を主体的にやっているのかというと、有川定輝先生の「技は諸手取呼吸法がつかえる程度にしかつかえない」という教えであり、実際に技をつかっていると、確かに呼吸法の程度にしか技と体がつかえないようだからである。例えば、呼吸法で新しい法則を身につければ、他の技もそれで上達するし、呼吸法が少し上達したなと思うと、不思議と一教や入身投げ等の技も変わってくるのである。
最近、これまでの片手取呼吸法、諸手取呼吸法に加え、坐技呼吸法をやるようになった。片手取呼吸法や諸手取呼吸法で得た法則でやればある程度満足できる結果になる。例えば、手と腹をしっかり結んで腹で手をつかう。体を陰陽十字でつかう。イクムスビの息で手や体をつかう。フトマニ古事記とアオウエイで手と体をつかう等の法則でやるのである。
これで相手と一体となり、相手を浮き上がらせ無力にすることができるのだが、何かいま一つ欠けていると感じていたのである。
しかし、或る時突然、坐技呼吸法はこれだと気がついたのである。その上手くいかなかった欠陥の原因がわかり、その解決法がわかったのである。それがわかれば、それまで坐技呼吸法が上手くいかなかったのは当然であるとも納得した。
欠陥の原因は、 (高皇産霊神・神皇産霊神両神合体の御霊)である。言霊では“お”である。“あー”で天に拡がった気が“お−”で地に下りる。
(高皇産霊神・神皇産霊神両神合体の御霊)である。言霊では“お”である。“あー”で天に拡がった気が“お−”で地に下りる。 をこれまでは、足底で複数の円を感じ、天之御中主神御霊と結んで地そして天と結び一体となり、しっかりした五体が出来るようにしてきた。
をこれまでは、足底で複数の円を感じ、天之御中主神御霊と結んで地そして天と結び一体となり、しっかりした五体が出来るようにしてきた。
しかし、 が意味するものは、力一杯に地に気を下ろすということであると悟ったのである。つまり、これまでは
が意味するものは、力一杯に地に気を下ろすということであると悟ったのである。つまり、これまでは を平面的に捉えていたわけだが、今度は上下の縦の動きということである。平面にこの縦の強い動きを表すために複数の○で表わしたのだと思うし、事実、それを実感するのである。
を平面的に捉えていたわけだが、今度は上下の縦の動きということである。平面にこの縦の強い動きを表すために複数の○で表わしたのだと思うし、事実、それを実感するのである。
それでは坐技呼吸法がどのように変わったのかというと、新坐技呼吸法は:
- 両手を出して相手としっかり結び、その態勢で、
- 腹を一方の膝に対して十字に返し、腹が太ももに載るようにし、地に全体重が下りるようにする。これが
 である。
である。
- 相手が掴んでいる手に全体重が掛かるので、掴んでいる相手の手にもこの力が掛かる。
- 後は立ち技の呼吸法と同様、

 で体と息をつかうと相手の他方の手が自然に上がり、相手が浮き上がってくる。
で体と息をつかうと相手の他方の手が自然に上がり、相手が浮き上がってくる。
しかし、坐って、自分の体重を地に落ちるようにするのは容易ではない。立ち技と同じように、布斗麻邇御霊とあおうえいの息づかいでやる必要がある。
最後に、これまで何故、ある程度上手くいっていたはずの坐技呼吸法に満足できなかったのかが分かったような気がするので記して見る。
人は、つまり稽古相手は、人工的な技には納得しないということである。人工的とは意識でやることである。従って、無意識で相手が動くようにしなければならないことになる。この度の坐技呼吸法で、相手が自然と浮き上がってくるような事である。思うに、これが魂の働きであり、技はすべてこの魂の働きになるように修業しなければならないということで、これを大先生は、合気道は魂の学びであるといわれているのだろうと思った。
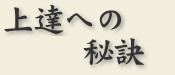

 上達への秘訣
上達への秘訣