【第23回】 生きている証しのために
合気道を稽古していて、若いうちは強くなろうとか、エネルギーの発散のためにやっていても、年をとってくると体力もなくなるし、闘争意欲もなくなってくる。若いときはあまり深く考えないし、稽古も勢いでできるが、高齢になると勢いだけでは稽古が続かなくなる。高齢者の稽古は、なにかしっかりした目標がないと続けるのが難しいだろう。
開祖は50〜60歳は「まだまだ鼻ったれ小僧だ」とよくいわれていた。50〜60歳ぐらいまでは真の合気道は分からないだろうから、自分を肉体的に徹底的に鍛え、自分の限界を知り、そしてその限界を押し上げる稽古をすべきだということだろう。自分の限界が分かれば、自分のできることと出来ないことが分かって来る。限界が分からなければ自分の可能性を誇大妄想したり、過小評価してしまい、結局はなにもできず、自分や他人に不満を持つことにもなる。
今は、容易に食べることもできるし、欲しいものも手にはいる。また、それほど苦労しなくとも生きていける。そんな時代に、暑さで汗をかきながらゼーゼー息を切らして稽古するのは意味があるのか考える人もあるだろう。
人は年をとってくると寂しくなる。何故ならば、死を意識するようになるからではないか。そして、自分とはなにか、自分の人生とはなにか、残りをどう生きればいいのかなど考えるようになる。
そこで、人は本能的に、生きている証しを残したいと思うようだ。実際、人はそれぞれ自分の生きている証しを残してきている。歴史的な仕事を残した人もいれば、家のため、子孫のため、あるいは自分のために生きた人もあるだろう。彼らの生きた証しは、書類や映像や口伝えなどに残されていたりするが、それだけでなくすべての人の生き様は、関係したすべての人のDND遺伝子に永遠に残っていくはずである。人は一度目にしたもの、耳にしたものは、自分が気が付かなかったり、そのとき思い出せないだけで、すべて脳に刻み込まれているらしい。催眠術でさっき見た部屋の様子を聞いたりすると、ふつうでは覚えていられないし、意識だけでは見えないものまで、無意識では見ているし、また覚えているのである。
NHKのドキュメンタリー番組で見たものだが、冬は誰も住まない日本最北端の礼文島の端にある鮑古丹(しゃこたん)に奥さんと二人だけで住む老漁師が、生きている証しのために毛筆でこれまで10,000以上の詩を書いていた。見事な書であり、素直な詩である。町に住む子供の同居しようという誘いも断って、町の外でより厳しい自然との共存を選んでいるこの漁師でも、自分の生きている証しを持ちたいと思うのかと印象的だった。いや、そういう環境にあるからこそ自分の生きている証しを意識して持とうと思うのかもしれない。これは人間の性であり、使命なのかも知れない。
合気道でも、自分の稽古をした証しが残せればいいだろう。それが自分の生きている証しにもなるはずである。
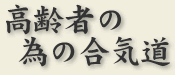

 高齢者の為の合気道
高齢者の為の合気道