【第567回】 武道感覚
昔の事もそれほど知っているわけではないので、今がどうのこうのと言える資格もないのだが、やはり自分の頃の以前と今を比べてしまう。
今気になることは、武道感覚である。合気道は武道であるわけだが、武道の稽古をしているという気持ちが段々薄れているように見えるのである。
合気道は愛の武道であるから、怪我しないようさせないように、仲良く和気あいあいとやればいいと思ってやっているように見える。
50年前と比べても世の中は大分変ったから、合気道の稽古も変わるのだろうが、本質的な部分は変えてはいけないと思う。
例えば、技は少しでも効くように錬磨しなければならない。相手の攻撃に屈しない。スキをつくらない等である。
従って、時代が変わろうが、世の中が変わろうが、この武道としての本質は追及しなければならないと考える。
技の追及と錬磨がなければ合気道にならない。合気道は技の錬磨によって精進するからである。ただ道場に来て稽古をやっていても技の錬磨にならない。真剣に技を練る稽古をしていけば分かるだろうが、技は宇宙の法則でできていること、その法則を見つけ、それを技で試し、その法則を身に着けることが技の錬磨ということなのである。
次に、相手の攻撃に屈しないようにすることである。如何にしっかり掴まれても、どんなに強く打たれても、それに屈せず、その攻撃と一体化して相手を導くことである。容易な事ではないが、肉体的、そして精神的に克服していかなければならない。相手に力を出させないために、しっかり掴ませないとか、もっと力を抜けなどの注文稽古では武道の稽古とは言えない。
三つ目は、スキをつくらないことである。受けで取りの手を掴みに行く場合でも、自分が技を掛ける際にも、スキがないように動き、技を掛けていかなければならない。諸手取りなどでよく見かけるが、相手の手を力一杯握って動かないようにしようと、相手の正面に立ったり、頭を下げ、腰を折って踏ん張るような姿勢で頑張っているが、取りの相手は片方の手が空いているし、足も自由に使えるわけだから、頑張っている本人は盤石だと思っているようだが、スキだらけなのである。真剣勝負の場であれば、やられてしまう。やられる感覚がマヒしているわけで、スキだらけというわけである。受けも武道的な感覚を身に着けなければならない。
合気道の形稽古は、技を掛ける取りと、受けの役割が決まっており、右左、裏表の4回が終われば受けと取りが交代することになっている。非常に公平で優れた稽古法だと常々感服している。しかし、あまり良くできているためか、形骸化もしているように見える。取りは相手を押さえたり倒したり投げればいいとし、受けは素直に受けを取っていればいいと受けを取り、次の自分の取りの番を待っている。
取りはスキがないように受けの相手に技をかけるわけだが、受けもスキのないように受けを取るだけでなく、本来の役割を果たしながら受けを取らなければならない。
本来の受けの役割とは、取りに攻撃を加える攻撃者であるということである。はじめに正面打ちとか、片手取りとかの攻撃をするが、受けの役割はそれだけで終わるものではないのである。最初から最後までの間に取りにスキがあれば、いつでもそこを攻撃できるようにすることである。
知らない稽古相手にスキがあると当身を入れたり、技を返したりするのは中々できないだろうから、気持ちで打ったり、返したりするのである。観のいい相手なら、やられたと感じるし、スキができないようにしていくはずである。それによってお互いが更に切磋琢磨できることになるのである。また、たまには気心の知れた相手に、当身など試してみるのがいい。
技を掛ける取りも、同じペースで技をつかうだけでは相手を納得させることは難しく、緊張感も生まれない。技は通常イクムスビの息づかいで収めるものだが、どの箇所でも一瞬で技を決めてしまうことができるように、技をつかっていくのである。ここから武道的な緊張感が生まれる。
時代や世の中が平和でやさしくなると、合気道の稽古も武道としての厳しさもなくなっていくようである。しかし、やさしく稽古をすればいいとはいえない。
これでは半分だけで不完全である。もう半分が加わらなければならない。やさしいの半面の厳しさである。やさしさと厳しさ、つまり武道としての厳しさとが相まって完全になるはずである。
合気道でのやさしさとは、相手を思い、相手の立場で技をつかうことである「愛」である。
「愛」は相手、厳しさは自分自身のためである。これが「武道の感覚」とうことになるだろう。
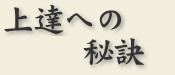

 上達への秘訣
上達への秘訣