【第222回】 極限から道が開ける
合気道は技の練磨を通して精進していく。しかし、ただ漠然と稽古を繰り返していても、技の上達、引いては合気道の精進は止まってしまう。
漠然と稽古をするということは、自分の小さな世界の殻の中で稽古をすることとも言えよう。つまり自分の限界の中でやることである。
そこには緊張もないから、上達もないし、真の喜びもないはずである。
新しい技をやったり、初めての相手と稽古をするときは多少緊張するだろうが、同じことをやったり、同じ相手との稽古ではあまり緊張をしないし、あまり気を入れてやらないようだ。例えば、準備運動などはその典型的なものだ。気持ちも力も極限まで入れてないので、関節の柔軟運動などの本当の運動になっていないのである。形だけをやっていては意味がない。
準備運動もそうだが、技を受けたり掛けたりする場合も、自分の極限でやらなければならない。何故ならば、極限の中でやっても自分は変わらないし、上達に繋がらない。上達とは自分の体力、能力、気力、眼力などなどの限界レベルが上がることと言えるだろうから、限界レベルを押し上げるためには、自分を極限まで追い込まなければならないことになる。
前述の手の関節を柔軟にしたり、鍛えるための準備運動にしても、自分の手の関節が壊れると思われるぐらいまで力を込めてやらなければならない。どんなに力を入れても壊れることはない。どんなに力をいれても、自分で自分の手、例えば、手首を壊すことはないし、出来るものでもない。心配しないで思い切りやればいい。
受けを取る場合も、安易に畳(床)を叩いて相手の締めを止めないで、自分の限界まで締めさせなければ、肩や肩甲骨のカスは取れず、カスで固まったままの腕のままとなり、技が効かないだけでなく、そのうち肩に痛みを覚えるようになるかもしれない。歯を食いしばって極限まで頑張らなければならない。極限まで頑張っていけば、そこの柔軟性と耐久力の限界はどんどん押し上げられることになる。
技を掛けるときも、体を自分が出来ると思う極限で遣うようにしなければならない。例えば、手の返し、腰の返し、重心の移動と掛け方などを自分の限界と思われるところまでやることである。手を90度々々返すならきっちりと返さなければならないし、入身転換で腰を180度返す場合もしっかりと返さなければならない。自分ではそれで十分と思っても、外から見ているとまだまだ中途半端なものだ。はじめは、自分が少しオーバーと思うぐらいで丁度いいようである。
初めは体のいたるところにカスが溜まっているので、その部位はなかなか思うように動かないものだが、限界を少しづつでも押し広げていけば、その内、動けるようになるはずだ。
心や息遣いでも常に極限で稽古をしていかなければならない。超スローにも超速でも出来るよう、自分の速度の遅速の限界を拡げていかなければならない。また、どんな相手、初心者や子供などとも一つに結びつく稽古ができなければならない。
技を超速や超遅速でやるためには、心(意識、気持)と息の遣い方が大事である。多少、相手の手刀や拳で叩かれても、その試練を乗り越えて心と息の遣い方を身につけていかなければならない。それが出来なければ、次の木刀や杖で打たせたり、切らせての稽古に進めない。稽古には常に次がある。
技も常に極限を目指さなければならない。真の真善美に少しでも近づくように、技を掛けていかなければならない。そこにも完成といいことはないわけだが、常に、その時点ではそれが最高ものであり、自分の限界であるものでありたいものである。
かって開祖は、稽古人から、そろそろ合気道の秘伝を教えて下さいというようなことを言われたのに対し、自分が今やっていることが最高のもので、これが秘伝である、というようなことを言われたと聞いたことがあるが、将にこのことであろう。
つまり開祖は、常に自分の極限で稽古をされていたということである。だから常にレべルアップがなされ、あのような超人的な技を遣えるようになられたのだろう。
上達したければ、極限から道が開けるわけだから、自分を自分の極限に追い込んで稽古をしていかなければならないことになるだろう。
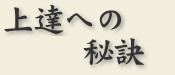

 上達への秘訣
上達への秘訣