【第371回】 武道の合気道
合気道は武道である。スポーツや遊戯とは違う。合気道は、スポーツとは違って、試合がない。相手に勝つために稽古するものではなく、自分に勝つために稽古するものである。だから、合気道は武道であるというのは正しいだろうが、武道である合気道には、武道としての何かがあってもよいだろう。
考えるに、武道にはスポーツにない厳しさがあるはずである。もちろん、スポーツも厳しい。トップレベルに入るためには血のにじむような練習をしなければならないし、試合の前日など眠れないものだ。
本格的にやれば、スポーツも体を壊したり病気になるほど厳しい練習に明け暮れるはずだ。だが、合気道は武道であるから、さらなる厳しさがあるはずである。
ではまず、武道として厳しいとはどういうことかを考えてみる。まず、厳しさは時代や世相によって変わるだろうし、厳しさの内容も変わるだろう。入門したころは開祖もお元気で、ハワイや地方の道場に教えに行かれていた。稽古人は少なく、白帯でも入門したその日から有段者と一緒に稽古をし、徹底的に関節をきめられ、投げられた。技や動き、体や息づかいなどは、投げられたり、受け身を取ったり、関節をきめられたりして覚えたものだ。
実は、それまではスポーツをやっていたので、はじめの頃は、武道の合気道はこんなものかと馬鹿にしていた。ところが、厳しい先輩たちに稽古をつけてもらう内に、これはスポーツどころではないと思うようになった。
スポーツは、高校生の時にインターハイではハイジャンプで県で優勝したぐらいだから、練習は相当やったのだが、合気道の稽古ではそんなものではなかった。日曜日も含めて毎日稽古に行ったし、行けば最低でも2時間分の稽古に出た。休み時間も稽古したから、3時間は稽古していたことになる。親しい先輩が勤めを終えて6時半(以前は、午後の稽古は3時、5時、6時半であった)の稽古に見えると、さらに6時半からの稽古もやったし、稽古時間後もまだその先輩と稽古していたものだ。
道場では休みもしないで、元気いっぱい稽古していたが、道場の門を一歩出たとたん、よく疲れで足が進まなくなったものだ。これでは、新宿まで都電(当時は都電が走っていた)を奮発しなければならないかと思ったりするのだが、その停留所までがまた実に遠いのである。2,3百メートルほどしか離れていない停留所であるが、3度ほどは道筋の家の前のごみ箱(かっては家の前にゴミ箱があった)に腰掛けて休みながら行く有様であったのである。
当時、年配の大学教授が我々若い仲間と一緒によく稽古したが、年寄り扱いしないで欲しいということだったので、我々はあまり遠慮しないで投げたり受けをとったりしていた。後で話を聞くと、その先生は我々との稽古の後で、家まではなんとかたどり着くが、玄関に入ったとたんに歩けなくなり、玄関から自室まで這っていったものだ、といわれていた。
また、ふだんの稽古では、膝行で稽古着はやぶれ、膝に血がにじむしで、袴をはけば多少は痛みが違うだろうと、有段者がうらやましかったものだ。しかし、有段者となって袴をはいてもその痛さは解消されず、袴もすぐに破れ、共布で何重にも縫わなければならなかった。
開祖が居られたときは、手を抜いた稽古、身の入らない稽古などしていると、開祖の雷が落ちたものだ。しっかり打ち、しっかりと持たせた稽古をしないのを見つかると、お説教ものであった。だが、座り技をやっているかぎりは、多少めちゃくちゃな稽古でも雷が落ちなかったので、稽古の多くが座り技であった。その時は苦痛であったが、今になると、そのころの座り技の有難さがよくわかる。
武道の厳しさ、武道の合気道の厳しさとはこんなものではないということは、開祖をはじめ、開祖の直弟子でもある師範の先生方から学んだ。
この頃の先生方のほとんどは亡くなられたが、どの先生方も非常に厳しかったと思う。先生方のほとんどは合気道を学ぶ前に、他のスポーツや武道をやっており、またその分野でも一流の方々であった。しかし、その先生方も、合気道はそれまでやってこられたものより厳しいと思われたことであろう。
厳しいとは、極端に言えば、命がけの稽古をされたていた、ということである。いかなる敵がいか様にかかってきても、対処できるような稽古と心構え、剣道や柔道や相撲や空手で攻められても、対処できるように稽古されていた、と思う。私が入門した当時は、まだ、いわゆる道場荒らしのようなことがある時代で、みんな気が張っていたし、本部道場は武道場であるという雰囲気があったと思う。
私の先輩などは、勤めの前に朝稽古に出、夕方、夕食後は家まわりの空き地で剣と杖の素振りを毎晩続け、時々、朝が明けるまで振り続けたと言われていた。鋭い眼をしていた上に、そのような疲れから目にクマができていたので、道場では人が寄り付かなかったようである。
しかし、時代がかわり、合気道を習う人も増え、時代に即した万人に無理なくできるやさしい稽古をするようになってきた。それでも、合気道はやはり武道でなければならない。
武道とは、命のやりとりを基本とする稽古法、修行法であるが、今の合気道の稽古にその武道の要素をどのように入れていけばよいか、を考えなければならないだろう。
合気道はまさしく武道である、と教えて下さった方のひとりに、本部道場の故有川定輝師範が居られる。この先生の稽古時間ほど緊張した時間はなかったし、先生と一緒に過ごす時間ほど緊張したことはなかった。稽古ではいつも先生から見られているような気がしたし、そばにいると気持ちが吸い取られていくようで、そしてスキがなく、たとえ師範の後ろから攻撃したとしても、とても駄目だろうなと思わされた。この先生は本当の武道家だ、といつもつくづく思ったものだ。
さて、合気道が武道であるためには、合気道の技の稽古を武道的にやらなければならないわけである。だが、武道的稽古とは、どういう稽古でなければならないだろうか。
有川師範の講習会を撮影したビデオ画面を見ていて、「正面打一教」で、これが武道的稽古というものであろうと改めて感じた。その幾つかを紹介しよう。
 常に攻撃の精神:相手の打ってくるのをただ漫然と受けるのではなく、自分から相手を迎えに行く。(写真)
相手の手を避けずに正面で迎え、いつでも相手を切り飛ばしたり、切り落としたり、切り引くことができるようにしておく。この攻撃の精神はいつでも出せて使えるように、最後まで持ち続けること。
常に攻撃の精神:相手の打ってくるのをただ漫然と受けるのではなく、自分から相手を迎えに行く。(写真)
相手の手を避けずに正面で迎え、いつでも相手を切り飛ばしたり、切り落としたり、切り引くことができるようにしておく。この攻撃の精神はいつでも出せて使えるように、最後まで持ち続けること。
 上記と関連して、当て身がいつでも入るように、態勢と心構えを保つ:
上記と関連して、当て身がいつでも入るように、態勢と心構えを保つ:
相手が正面打ちで打とうとするとき、①一歩進んで相手のあごを突きあげたり、顔面を打つ(写真)
②肘を抑える手で相手の脇腹を突く ③肘を抑えた反対側の手で相手の手首を抑えている人差し指は相手の顔面に向き、その手は相手の顔面をいつでも突けるようにする(写真)
③肘を抑えた反対側の手で相手の手首を抑えている人差し指は相手の顔面に向き、その手は相手の顔面をいつでも突けるようにする(写真)
④床に相手を沈めるとき、自分の内側の膝で相手の脇腹を打つようにする。
ここで有川先生は、今回は当て身の稽古ではないので、詳しいことは言わないとのことであったが、実際にはまだまだ当て身が入るのだろうと考える。 急所を抑える:相手の力が抜けてしまうような点が、人体にはあるようだ。そこを上手におさえることが、大事なようであり、それがなければ、腕力で抑えなければならないことになる。
急所を抑える:相手の力が抜けてしまうような点が、人体にはあるようだ。そこを上手におさえることが、大事なようであり、それがなければ、腕力で抑えなければならないことになる。
一教で相手の手首をおさえるときも、急所を親指と小指を中心に掴まなければならない。(写真)
指先と腰腹を結び、腰腹の力で、腰腹と手先を十分につかわなければ、急所をおさえることはできない。おそらくおさえるところは、すべて急所でなければならないのだろう。合気道の技は宇宙の営みを形にしているといわれるから、そのようにできているのだろう。 微妙な指の使い方:肘をおさえた反対側の手で、相手の手首を抑える際には、手で掴むのではなく、小指を巻き込むようにして、親指と二本(出来れば小指一本)で相手の手首をおさえるようにする。このとき、上述のように、小指は相手の急所をおさえ、人差し指は相手の顔面を捉えており、いつでも顔面に当て身を入れられる。(写真)
微妙な指の使い方:肘をおさえた反対側の手で、相手の手首を抑える際には、手で掴むのではなく、小指を巻き込むようにして、親指と二本(出来れば小指一本)で相手の手首をおさえるようにする。このとき、上述のように、小指は相手の急所をおさえ、人差し指は相手の顔面を捉えており、いつでも顔面に当て身を入れられる。(写真)
現代の武道の合気道を稽古するためには、①自分を鍛えるために稽古していることを自覚する ②自分の限界は勿論のこと、稽古相手の限界(例えば、関節の可動範囲)の精々紙一重上でやる ③肉体的、魄は相手に合わせて制御してつかわなければならないが、気持ち(魂)では、自由で最高の技をかけなければならない ④より厳しく、繊細に身体をつかい、宇宙の営みの形に少しでも近づくように技をかけていかなければならない。
このような稽古が現代の武道の合気道の稽古かと思う。
最後に、武道とは常に命のやり取りが根底にあり、スキをつくらないように、また少しでも技が効くように、限りなく厳しく体と心をつかっていくものだと思う。それ故、武道の稽古は限りなく、終わりがないわけである。合気道が武道であれば、このような、またはこれ以上の、自分に厳しい稽古をしていかなければならないのではないだろうか。
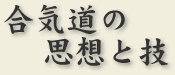
 合気道の思想と技
合気道の思想と技
