【第156回】 真空の気
合気道は植芝盛平翁がつくられたが、武道であり宗教であり哲学ということができるだろう。開祖の生誕から100年ほどであるから、合気道は新しいと言えるが、その根は神代から続くので、古いとも言える。従って、合気道は新しくて古く、古くて新しいと言える。
合気道には世界大会やオリンピック等の試合がないにもかかわらず、世界に普及している。闘争心旺盛な国々にまでこの試合のない合気道が受け入れられているというには、何か大きな理由があるはずである。
人は誰でも、性別、年齢、国とは関係なく、何かを目指して生きようとしており、生きているように思う。合気道はそれを分かり易く説く道ということで、多くの人たちが稽古に励んでいるのではないだろうか。合気の道は、真理を見つけるための道である。真理を「神」ともいう。合気道は技を通して道を見つけ、道を進み、そして「神」を見つけようとするものと言える。
「道」を見つけるためには、技をきちっとやらなければならない。技が出来なければ道が見つからず、道に乗れない。しかし、技をきちっとやることは容易ではない。開祖はもうおられないし、開祖から直接教わったお弟子さん(師範)もどんどん少なくなってきている。心して稽古(いにしえをみる)しないと違うものが出来てしまうことになる。
開祖は、技の具体的な説明はほとんどされなかった。合気道には試合がないし、技の遣い方に決まりもないので、自由にできる。相手に害を及ぼさない限り好きにできるわけである。
しかし、自由に好き勝手に技を遣ったのでは、上達は止まってしまい、道に入れないことになる。この合気道の自由の中には、何か大きな規制があると思う。規制とは、やらなければならないこととも言えるだろう。上達の扉を開けるカギのようなものである。例えば、「真空の気」というカギがある。
「身の軽さ、はやわざは真空の気を持ってせねばなりません。空の気は引力を与える縄であります。自由はこの重い空の気を解脱せねばなりません。これを解脱して真空の気に結べば技が出ます。」と開祖が言われているので、この「真空の気」が分からなければ技が出来ないことになる。
しかしながら、開祖は「真空の気」とは何か、どうすれば「真空の気」を技に結びつけることができるかを、我々に伝授されなかった。ただ「真空の気」のキーワードだけが残っただけなので、なかなか用をなさないというのが現状である。
この「真空の気」のカギは、開祖の言葉の中にあるようだ。開祖は「解脱するには心の持ちようが問題となってきます。この心が己の自由にならねば死んだも同然であります。弓を気一杯に引っ張ると同じに、真空の気をいっぱいに五体に吸い込み、清らかにならなければなりません。
 清らかなれば、真空の気がいちはやく五体の細胞より入って五臓六腑に食い入り、光と愛と想になって、技と力を生み、光る合気は己の力や技の生み出しではなく、宇宙の結びの生み出しであります。」と『合気真髄』に書かれている。
清らかなれば、真空の気がいちはやく五体の細胞より入って五臓六腑に食い入り、光と愛と想になって、技と力を生み、光る合気は己の力や技の生み出しではなく、宇宙の結びの生み出しであります。」と『合気真髄』に書かれている。
「真空の気」のカギの一つは、「心」である。自分の心を自由にすることである。自由とは、なにものにも捉われないということである。相手が大きいとか、強いとか、怖いとかという心をなくすことであろう。心が捉われて自由な心でなくなると、体が動かなくなり、死に体となると言われている。
二つ目のカギは、腹と肺に宇宙のエネルギーを吸い込むことである。実際に吸い込むのは空気だろうが、イメージとしては宇宙に充満していると言われるエネルギー、現代の宇宙科学でいう、暗黒物質と暗黒エネルギーということになろう。
このエネルギーを五体の隅々まで行き渡らせ、充満させることである。このエネルギーが充満した感覚を称して、開祖は「弓を力一杯に引き絞ったときの感覚」と言われている。
弓道で弓を引くときのことを、「息を吸い込んだら腹壁がふくらむようにゆっくりと息を押下げ、そこでしばらく止め、それから息をゆっくりと、出来るだけ一様に吐き出す。この呼吸があらゆる精神力の源であることがわかり、リラックスすればするほど、ますます沢山の力が湧いてきて、手足に行き渡るようになる。吸気は結合と連合。息をいっぱい吸って止めるとき、一切がうまく働くのです。呼気はあらゆる限界を克服することによって完成するのです」と言う。(『弓と禅』 オイゲン・ヘリゲル)
尚、普通の人には太陽は眩しくじっと見つめることは出来ないものだが、開祖は太陽を見ても眩しくないと言われていた。弓を引っ張る時と同じに、息をいっぱいに五体に吸い込んで太陽を見ると眩しくなくなる。この息遣いは大事なようだ。
開祖は具体的な説明はなさらなかったが、キーワードとそれを説くカギを残して下さっているのである。「真空の気」だけでなく、他の難解なキーワードにもそれを解くカギがあるはずである。こころして研究し、それを体で体得していかなければならないだろう。
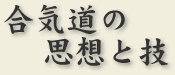
 合気道の思想と技
合気道の思想と技
