【第99回】 力(りき)まない体をつくる
武道でも「力む(りきむ)」ことはよくないとされる。「力む」とは、力をこめること、息をつめて力を入れることである。よく見かける典型的な力みの例は、二教裏と木刀の素振りでの力みである。
力むと、力が出ないし、体が働かなくなる。何故かというと、
- 力んだ部位、それに伴って体もこわばってしまい、力が内向きに働き、外に向かわないので、力が出ないし、体が十分に機能しない。
- 表層筋が硬くなるので、深層筋の働きを止めてしまい、真の力が出ない。
- 息をつめてしまうので、呼吸が乱れる。
- 気持ちが内にとどまり、スキが出来る。
- 力むと、力んだ部位だけを使うことになり、他の部位とのつながりが切れ、体全体の力が使えない
鍛錬棒を両手で握り、ゆっくりと大きくまわしながら振る。肩や腕に力を込めないように、背中と腰で振るようにする。大きく振るためには、腕で顔を洗うように振るといい。また、肩を貫くことと、息の使い方には注意しなければならない。肩を貫くには、胸鎖関節が腕の支点となるように、菱形筋を使う。要するに肩甲骨を動かすように振ればよい。剣や棒を振る場合、持っているところを動かすと力みになる。その部分を使わずに対極(背中や腰、脚)を動かさなければならない。
息の使い方は、棒を振り上げて下ろすところまでは息を吸い、最後に止める(切る)ときに吐くのである。手と足は同じ側が進み、手と足の重心が左右規則正しく移動するようにしなければならない。
もちろん、ある程度の力がなければならないので、初めのうちは多少腕が痛くなるだろうが、焦らず鍛錬を続けることである。鍛錬棒や木刀を振って、肩が痛いとか、腕がはるのは、まだ力んでいるからである。それが無くなるまで鍛錬するしかない。
 大きくスムースに振れて、腕に鍛錬棒の重さを感じなくなれば、力みが取れたことになろう。剣豪小説などで、豪傑が重い槍や鉄棒を縦横無尽に振り回す場面がよく出てくるが、ひとは相当重い得物を振り回すことができるようだ。山内一豊、福島正則、加藤清正等々は槍の使い手として知られているが、当時の槍をみると相当長くて、重い。しかも、馬上でも遣ったという。手先だけで振れるようなものではない。稽古の量もすごかっただろうが、力みを取って、手先ではなく、背中や腰で振ったに違いない。
大きくスムースに振れて、腕に鍛錬棒の重さを感じなくなれば、力みが取れたことになろう。剣豪小説などで、豪傑が重い槍や鉄棒を縦横無尽に振り回す場面がよく出てくるが、ひとは相当重い得物を振り回すことができるようだ。山内一豊、福島正則、加藤清正等々は槍の使い手として知られているが、当時の槍をみると相当長くて、重い。しかも、馬上でも遣ったという。手先だけで振れるようなものではない。稽古の量もすごかっただろうが、力みを取って、手先ではなく、背中や腰で振ったに違いない。
また、こころの力み、精神的な力みもよくない。特に緊張である。緊張とは精神(こころ)の力みと言えるだろう。体も心も力みをなくすように鍛錬しなければならない。
Sasaki Aikido Institute © 2006-
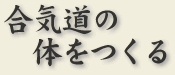

 合気道の体をつくる
合気道の体をつくる