【第767回】 布斗麻邇(ふとまに)の御霊 続
前回の「第766回 布斗麻邇(ふとまに)の御霊」に引き続き、この布斗麻邇を具体的にどのように技につかえばいいのかを記すことにする。これで現わした技こそ、魄の次元から脱する事が出来ると思うしだいである。
具体的にここからどのように技を生み出していくかというと、前回示した「布斗麻邇の御霊」と大先生の布斗麻邇の御霊の教えを照合しながら技にするのである。「布斗麻邇の御霊」の順に、大先生の教えを重ね合わせて技をつくり、姿を現していくわけである。
分かり易いように、その両方を再度ここに掲載する。
「布斗麻邇の御霊」
 |
|
「合気は天の浮橋に立たされて、布斗麻邇(ふとまに)の御霊、この姿を現すのであります。これをことごとく技にあらわさなければならないのであります。これはイザナギ、イザナミの大神、成りあわざるものと成りあまれるものと・・・。 自分の中心を知らなければなりません。自分の中心、大虚空の中心、中心は虚空にあるのであり、自分で書いていき、丸を描く。丸はすべてのものを生み出す力をもっています。全部は丸によって生み出てくるのであります。きりっと回るからできるのです。武術は魂さえ、しっかりしていればいくらでもでき、相手をみるのではない。みるから負けるのであります。何時でも円を描きだし、ものを生みだしていかなければならないのです。(神髄 P153,154)」
先ずここで大先生が布斗麻邇(ふとまに)をどのように謂われているかというと、「合気は天の浮橋に立たされて、布斗麻邇(ふとまに)の御霊、この姿を現すのであります」と、技で布斗麻邇(ふとまに)の御霊の姿をあらわさなければならないと言われている。
更に、大先生は『合気神髄』『武産合気』で、布斗麻邇とは、
○気体と気体と正しく打ち揃った美しい様を布斗麻邇という。
○布斗麻邇とは気の動きでいうと「う」ということだまの御働きによる。だから「う」のことだまの御働きを神習わなければいけない。
と謂われているから、これも念頭におかなければならない。
「布斗麻邇の御霊」の最初は
 である。「天之御中主神御霊」である。先ず、技をつかう際は天之御中主神になるということである。これを大先生はここで、「自分の中心を知らなければなりません。自分の中心、大虚空の中心、中心は虚空にあるのであり、自分で書いていき、丸を描く。丸はすべてのものを生み出す力をもっています。全部は丸によって生み出てくるのであります。」と教えておられる。何もない大虚空や自分に中心(ヽ)を作るのである。腹をぎゅっと締めると出来る。そして締めた腹を緩めるとお腹、そして体中に気が満ちてきて体はどんどん丸くなる。それが
である。「天之御中主神御霊」である。先ず、技をつかう際は天之御中主神になるということである。これを大先生はここで、「自分の中心を知らなければなりません。自分の中心、大虚空の中心、中心は虚空にあるのであり、自分で書いていき、丸を描く。丸はすべてのものを生み出す力をもっています。全部は丸によって生み出てくるのであります。」と教えておられる。何もない大虚空や自分に中心(ヽ)を作るのである。腹をぎゅっと締めると出来る。そして締めた腹を緩めるとお腹、そして体中に気が満ちてきて体はどんどん丸くなる。それが である。従って立体的な丸であって、平面的は円ではない。
である。従って立体的な丸であって、平面的は円ではない。 が膨らんでいくと、両足が地を圧するようになる。そして気が回り出す。それが
が膨らんでいくと、両足が地を圧するようになる。そして気が回り出す。それが である。これを大先生はここで「自分で書いていき、丸を描く。丸はすべてのものを生み出す力をもっています。全部は丸によって生み出てくるのであります。きりっと回るからできるのです。」と言われているのだろうと思う。
である。これを大先生はここで「自分で書いていき、丸を描く。丸はすべてのものを生み出す力をもっています。全部は丸によって生み出てくるのであります。きりっと回るからできるのです。」と言われているのだろうと思う。

 である。「伊邪那岐神の御霊」「伊邪那美神の御霊」「伊予の二名の島」である。
である。「伊邪那岐神の御霊」「伊邪那美神の御霊」「伊予の二名の島」である。正面打ち一教で説明する。半身で立っているので、腹は乾、前足は北、前肩は東北を向くことになる。
 から、半身で乾(西北)にある腹と手を北の正面に返す、これが
から、半身で乾(西北)にある腹と手を北の正面に返す、これが で、次に手を手先の方に伸ばす。これが
で、次に手を手先の方に伸ばす。これが であると考える。そして伸ばし切った処で、縦に伸ばしてある手先、腕、腰腹を横に拡げると他方の手先、腕、腰腹は伸び両手で玉を抱くような感じになる。これが
であると考える。そして伸ばし切った処で、縦に伸ばしてある手先、腕、腰腹を横に拡げると他方の手先、腕、腰腹は伸び両手で玉を抱くような感じになる。これが である。これを大先生は、「これはイザナギ、イザナミの大神、成りあわざるものと成りあまれるものと・・・。」と言われておられるはずである。
である。これを大先生は、「これはイザナギ、イザナミの大神、成りあわざるものと成りあまれるものと・・・。」と言われておられるはずである。更に、その横に拡がった横の動きに合わせて、息を吐きながらつかう手と体の形が
 「筑紫島」となり、そして最後に地に着けて抑える姿が
「筑紫島」となり、そして最後に地に着けて抑える姿が 「大八島国」である。この「大八島国」を山口志道は、「天地人、容(かたち)成って、水火(いき)を為すの御霊を謂う」と言っている。つまり、天と地と人が一つになるということであると考える。
「大八島国」である。この「大八島国」を山口志道は、「天地人、容(かたち)成って、水火(いき)を為すの御霊を謂う」と言っている。つまり、天と地と人が一つになるということであると考える。尚、「布斗麻邇の御霊」には、○と□がつかわれているが、○は息を引く・入れる、吸うで、□は息を吐くのである。従って、
 「天之御中主神御霊」から
「天之御中主神御霊」から 「伊予の二名の島」までは、息を引き続けなければならない事になる。但し、この息は気に代わらなければならないと思っている。
「伊予の二名の島」までは、息を引き続けなければならない事になる。但し、この息は気に代わらなければならないと思っている。合気道の技はすべて、大先生が言われるこの「布斗麻邇(ふとまに)の御霊、この姿を技にあらわさなければならない」と確信した次第である。
参考文献 「言霊と日本語」今野真二著 ちくま新書
Sasaki Aikido Institute © 2006-
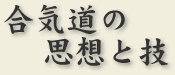
 合気道の思想と技
合気道の思想と技
