【第232回】 一教の腕をつくる
合気道はその技を練磨して精進するが、合気道の体と合気道の体遣いができなければ、技の練磨に限界の壁が立ちはだかる。
ということは、限界の壁が立ちはだかったならば、体をさらに鍛え、体をつくり、体の遣い方を変えれば、その壁を乗り越えることができるということになろう。
合気道での基本中の基本技は一教と言われるし、そう信じている。一教がしっかりできなければ、他の技もその程度にしかできないと言ってよいだろう。例えば典型的な例として、小手返しがある。一教のしっかりした手で相手の手を抑えることができなかったり、小手を反せないと、他方の手で相手の手首をいじめてしまうのである。これでは小手返しではなく、「手首苛め」になってしまう。
実際、一教ができて来ると、それに応じて小手返しもうまくなってくるものである。
一教は、技を掛けるのも、受けを取るのも、一番大変である。腹と結んだ指先に力を集中して、相手の太い腕を螺旋で抑えなければならないし、受けを取る場合も、腕と脇腹は引き延ばされ、腕は極限まで螺旋で返されるので、取りも受けも相当気持ちを集中し、呼吸に合わせてやらなければならない。
人は本質的に苦労するのが嫌なようだから、一教でもなるべく楽にやろうとしてしまうのだろう。そうすると腹と指先が結ばないし、指先に力が集まらないし、また、受けをしっかり取らなければ、腕や肩のカスがこびりついたままになってしまうから、合気道の体はできてこないことになる。
ということで、一教の腕をつくらなければならないが、まず一教とは何か、二教とどう違うのかを一度考えてみなければならないだろう。
かつて我々が合気道を習い始めたころは、一教を「一教腕抑え」、二教を「二教小手回し」といっていた。開祖がおられたこともあって、稽古する技は基本技が多く、その内でも一教腕抑えは多かった。今考えると稽古では、まず腕を鍛え合うことが中心であったように思う。腕を鍛えることによって腹や腰を練っていくということであったのだろう。だから、先輩たちの誰もが、腕が太くて、しっかりしていた。
先輩は、我々後輩がどれだけ進歩したかを見るために、よく手首や腕を握ってみたものだ。そして、だいぶ太くなってきたなとか、まだまだ細くて駄目だからもっと鍛えろとか、言われていた。腕の太さと体のでき具合は関係があるのだろう。
腕は、ふつう考えられているより重要なようだ。その腕を鍛えるには、一教が最適であるが、一教というものにはもう少し広い意味があると考える。ふつう、一教とは「正面打ち一教」とか「片手取り一教」とかの技をいうが、一教を腕抑えとすれば、腕を抑えて相手を崩したり抑えたりする技の遣い方と言うことができるだろう。
この理で二教を定義すると、二教は「小手回し」だから手首の関節を極めて、(小手を回し)相手を崩したり抑えたりする技の遣い方といえるだろう。
肩取りや胸取りで、一教腕抑えで技を掛けるのは、手首の関節を極める、いわゆる二教を遣うよりも難しいものだ。正面打ちでも、片手取りでも、二教で手首を極める方が、腕抑えよりはるかに容易であるはずだ。人の手首は腕より弱いからである。しかし、一教腕抑えで、手首ではなく腕を抑えてきちっとできなければ、二教もできるものではない。一教がしっかりできて、はじめて二教もできるものである。
一教腕抑えが重要なことを理解できれば、他の技も腕抑えで稽古してみるとよい。小手返しでも、四方投げでも、相手の腕を抑えて極め、また二教小手回しでも、手首の関節を極めるのではなく、相手の腕を(絞り込んで)抑えて極めるような稽古をするのである。
開祖は一教(腕抑え)までしか教えられなかったと聞いたことがあるが、上記の意味でそうかもしれない。一教が満足にできないものに、先を教えても意味がないと思われたか、または、一教ができれば、あとは稽古をやっていけば、二教も三教もできるようになるだろうから、まずは一教に、とされたのかも知れない。
いずれにしても、一教が大事である。まずは、一教腕抑えで、一教の腕と体をつくることである。
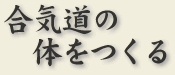

 合気道の体をつくる
合気道の体をつくる