【第19回】 たるみのない動き
合気道の稽古をしている人を見ていると、ひと目で上手な人と下手な人が分かるものだ。それは、強い弱いとか、古いとか新しいとかの問題ではない。勿論、一般的に古い人、強い人は上手であるが、常にそうではないということである。上手下手にはいろいろな判断基準があるが、その内の一つに"たるみ"がある。それは特に受けを取っているときによくわかる。
初心者は大抵相手と接したところから"たるみ"があって、相手がまだ生きている状態で技をかけようとする。技は、相手と充分結んでからでないとかからないものである。
相手と接したとき、相手と結ぶことで相手の動きを殺しても、技を終了するまでの間に又たるみがでやすいものである。たるみがでると、相手は生き返ってしまうので、相手と再び結んで制することをゼロからやり直さなければならなくなる。
上手下手とは、このゆるみがあるかないか、どれだけあるかによっても判断できる。例えば、四方投げでは転換して投げる瞬間、相手の手がたるみがちになるが、それでは相手に引っ張られるところんでしまうし、くるっと回られて逃げられてしまう。特に、半身半立ちの四方投げは、初めから最後までたるみがちである。
たるみのないということは稽古だけではなく、日常の生活でもそうあるべきだろう。たるみがあるということは、スキがあるということにもなるだろう。合気道の開祖は、これを合気道の稽古の中はもちろん、日常生活の中でも"たるみ"が出ないように、厳しさをもって生きておられた。内弟子にはスキがあればいつでもかかってこいと言われていたし、内弟子もなんとか打ち込めないか虎視眈々と狙っていて、常に緊張の毎日であったようだ。
稽古で技をかけるときも"たるみ"は出る。はじめは10も20も出るだろうが、それを少しでも少なくし、だんだん無くすように心懸けるのも大事な稽古である。相手を投げたり、押さえれたりすれば、プロセスはどうでもいいというのでは、寂しいかぎりであり、相手も決して納得してくれないことだろう。
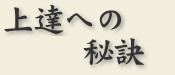

 上達への秘訣
上達への秘訣