【第150回】 腕の力を貫く
火事場の馬鹿力といわれるように、人には予想以上の大きな力があるはずである。問題はその潜在的な力を、必要なときに自由に取り出すことができないことである。開祖はこれを自由にできたのだろう。
凡庸なる我々稽古人は、一度に潜在的な力全部を出し、遣うことは無理なので、少しずつでも自分の潜在的に眠っている力を呼び起こし、それを遣うしかない。そのためには、力が出るような体の遣い方を研究しなければならない。
日常生活でもそうだが、武道においても、相手を崩したり倒すのは、ほとんどが手であるが、習慣的に、日常遣っている腕の力に頼って手を遣ってしまうことになる。腕の力でやれば、経験的にある程度の力は確実に出せるが、体(体幹)からの力や潜在的な馬鹿力に比べれば、比較にならない力である。また、この腕の力は腕力ともいわれるように、あまり質のよい力ではない。
手に集まり、わざ(技と業)に遣われる力には、手、腕からの力、腰腹からの体幹からの力、足・下肢からの力、地からの抗力などがあるだろう。手・腕の上肢の力だけを遣っていたのでは、それよりもっと大きな力がでるはずの部位からの力が遣えないので、「わざ」が効き難いことになる。また、手・腕の力を遣うということは、手・腕のところで力んでしまい、そこで他からの力をシャットアウトするということである。この力んで、力をシャットアウトするのが、真の力が出ない問題と考える。
力むなといっても、力まなくなるものではない。また、人が教えられるものでもない。自分で実感するほかはない。手・腕が力まないようにするには、いわゆる手・腕が貫けなければならない。貫ければ他の部位と繋がり、体幹、下肢、地からの力を、手先まで貫くことができる。
腕が貫けたかどうかを知る目安の一つは、自分の腕に重さを感じるかどうかである。腕の重さは2〜3kgある。結構重いはずである。長い間腕を下ろしていれば、疲れて腕組みをしたり手を後で組んだりする。無意識の内に、腕の重さを感じているのである。
この腕の重さを意識して、手・腕に感じるのである。腕が重くなると、不思議なことに水に浮きやすくなる。風呂でもプールでも、腕が浮くのである。重くなると、軽くなるのである。腕に力みがあり、力が貫けていない「力み腕」だと、浮き難いものである。物事に正反対があるから面白い。その極端な例は、死体である。完全に力みがなくなったから、水に浮くのである。生きていると力みがあるので、浮かずに沈む。そして、死ぬ。死ぬと浮いてくるのである。
力を貫いた腕は強い。中国(台湾、香港)のカンフー映画でキョンシーというのが出てくるが、死んだ子供たちが夜になると起き出して、生きている武道家と戦う。死んでいるのに、これが強いのである。体は死んでいるが、力みのない“死んだ“手足を遣うから強いのである。
 「キョンシー」が面白いのは、死人は強いと考える中国人の考え方である。死人は動かないが死人は重い。葬式で死人を数人で担ぐが、お棺に固定されているから担げるものの、死人はなかなか担げないだろう。もし死人が倒れてきて下になったら押しつぶされるだろうし、腕を持ち上げて離せば、何の躊躇もなく勢いよく落ちるだろうから相当の重さと衝撃があるだろう。もし、この死人のように力みを取った状態を、生きている人間が稽古の中で再現できれば、通常とは量も質も違う力が出るはずである。
「キョンシー」が面白いのは、死人は強いと考える中国人の考え方である。死人は動かないが死人は重い。葬式で死人を数人で担ぐが、お棺に固定されているから担げるものの、死人はなかなか担げないだろう。もし死人が倒れてきて下になったら押しつぶされるだろうし、腕を持ち上げて離せば、何の躊躇もなく勢いよく落ちるだろうから相当の重さと衝撃があるだろう。もし、この死人のように力みを取った状態を、生きている人間が稽古の中で再現できれば、通常とは量も質も違う力が出るはずである。
腕の力を貫くためには、力みを取るほか、手(手首、前腕、上腕、肩甲骨、胸鎖関節)の節々にあるカスをとらなければならない。カスは体の節々の錆のようなもので、使わなければ溜まってしまうものである。節々を動かして“油”を差し、スムースに動くようにしなければならない。合気道のわざ(技と業)、呼吸法、転換法などをきちっとやれば取れるはずである。
死んでからでは、「キョンシー」のようにいくら強くなっても面白くない。生きている内に、そのような力が出るよう、腕の力を貫く稽古をしなければならないだろう。
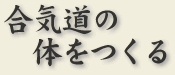

 合気道の体をつくる
合気道の体をつくる