【第191回】 骨盤の遣い方
前回は「骨盤を意識する」というテーマで、体の安定や力を出すためには骨盤を意識しなければならないと書いたが、今回も引き続き「骨盤」をテーマとする。「骨盤」は、普段はあまり意識しないものだが、体の研究をしていくと、非常に重要な体の部分であることが分かってきたからである。
合気道の稽古では技の練磨を通して上達していこうとするが、同じような五体をもっている人間にそれほど大きい力の差はないものである。確かに相対稽古の相手との力の差は若干あるだろうが、質的には同じであるし、違うというほどの差ではない。勿論、朝青竜のような人と比べれば違うだろうが、それは力が出せるように稽古をした結果、力が出るようになったのである。そのようになりたければ、それなりの稽古をしなければならないだけの話である。
合気道の稽古でも力は要るし、力はあった方がいいはずだ。しかし、そうは分かっていても、力は中々出せないものだ。出しても相手とほぼ同じで、あまり差がないはずである。その理由の一つは、遣いやすい体の部位を、日常生活の感覚で遣っているからと言えるだろう。
日常生活の感覚での力の遣い方の一つは、日常生活で遣っているように、手先の末端を主体的に動かして遣い、また手足をバラバラに遣うことであろう。二つ目は、日常生活ではあまり使わない体の部分を遣わないことである。日常生活ではその部位を遣わなくても、あまり支障がないから、遣う必要がないのである。その典型的な部位が、「肩甲骨」と「骨盤」であろう。
若者と老齢者の歩行を比較すると、若者は早くも遅くもスムースに安定した姿勢で歩けるが、老齢者の歩行はロボット(注:今のロボットは走ったり、起き上ったり出来るから、子供の頃のブリキロボットを想像してもらいたい。でないと、ロボットに失礼になるだろう。)に近づいてくる。
この差はどこに一番あるかというと、「骨盤」にあると思う。街を歩く子ども、若者、老人の腰のあたりを後ろから見て比較してみると、若者の「骨盤」は柔軟で、老齢者の「骨盤」は固まってきているのが分かる。「骨盤」が固まれば、股関節も固まることになるだろうから、「骨盤―股関節―脚」が一つのかたまりのようになり、ロボットのようにしか歩けなくなるのであろう。これを見ても、体の中心である「骨盤」が柔軟であるか、固まっているかが重要であることがわかる。
「骨盤」が硬くなった老齢者も、若いころには柔軟性があったはずであるから、はじめから固まっていたわけではなく、だんだんと固まってきてしまったはずである。不幸なことに「骨盤」の重要さに気がつかず、柔らかくすることをしなかったのであろう。
日常生活では、「骨盤」の不具合や損傷などでその重要性を認識するぐらいだが、パワーが必要な武道やスポーツでは「骨盤」の重要性を認識し、その遣い方を研究することが大事であると思う。相撲を見ても、体の中心としての「骨盤」を柔軟に遣って力を出している。
合気道でも力は「骨盤」から出るはずである。しかも動き始めるのも、体の中心であるこの「骨盤」からであるようだから、体の末端の手先や足の動きも「骨盤」からの力が伝わって動くことになるはずである。
「骨盤」からの力を手足の末端まで効率よく伝えるには、体を捻らないことである。これは武道の鉄則である。体を捻じれば力が出せないだけでなく、腰を痛めることになる。多くの稽古人が腰を痛めてしまうのは、腰を捻って遣ったからであるといえる。
腰を捻るとはどういうことかというと、「骨盤」の左右の線と両肩の左右の線が横からみれば平行線、上から見れば一直線を保たれていなければならないのだが、その平行線や一直線が崩れるということであろう。従って、「骨盤」と肩が平行線を保つためには、中心である「骨盤」が動くに従って、肩も動かさなければならないことになろう。つまり、体を面で遣うことにもなる。
「骨盤」は、仙腸関節などを動かさないと、その周辺の筋肉が硬直したり癒着してしまい、だんだん固まってくる。固まった「骨盤」で腰を捻ったりすると、「骨盤」は動かないで、「骨盤」の上にある腰椎を遣うことになり、そこに負担がかかって腰を痛めてしまうことになるだろう。腰を痛めないためにも骨盤」周辺の筋肉をほぐすなどし、「骨盤」を動きやすくするようにすればいいと考える。
「骨盤」を柔軟にする方法の一つに、階段や坂をのぼるとき、地に着いた足の反対側の「骨盤」をあげるように歩くといいようだ。「骨盤」がシーソー(ぎっこんばったん)運動をすることになり、この部位が柔軟になるわけである。山歩きはもっと効果的である。「骨盤」が柔軟になれば、股関節も柔軟になり体を落とすことができるようになる。これを武道では体を沈めるというのだろう。
「骨盤」は予想しているより大事な働きをするようである。日常生活でも稽古でも、「骨盤」を意識して遣ってみてはどうだろうか。
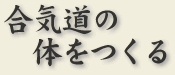

 合気道の体をつくる
合気道の体をつくる