【第15回】 関節を鍛える
合気道は相手を破壊したり、やっつけたりするものではない。魄の武道ではなく、魂を磨く武道であると言われる。
しかし、開祖も言われていたように、魄を土台にした魂の修行でなければいけないわけで、魄、つまりしっかりした肉体がなければ修行にならないのである。
開祖晩年(昭和36・7年頃)の頃は、まだまだ柔術的な技も多く、相手を制することを主眼にした稽古をする人も多かった。相手を制するためとは、まずテンポを早くして息をあがらせてしまい、参らせる。次は関節技で激痛を与え参ったと言わせることであった。そういう人を相手の時には、参らせられないためにまず受身の稽古をした。現在のように本部道場でも稽古人はそう多くなかったので、相手に投げられるまま逆らわずに前受身、後ろ受身をとれた。稽古が終わっての自主稽古でも、そこに居合わせた先輩に投げてもらった。受身から息の使い方、力の抜き方などが分かったし、肺や心臓もしっかりしたようだ。1−2年すると大体の人の受身が取れるようになったし、息も上がらなくなった。
さらに、関節を鍛える稽古もした。特に、手首関節と肘関節である。われわれの仲間うちでは、当時の上手い下手はほぼ関節の強さで決められるものとされていた。関節技が効かなくなると、強いということになっていた。また、関節が強くないと先輩は本気で相手にしてくれなかったので、二教、三教、四教で関節を鍛えた。稽古が終わってから仲間と10回、20回とお互いにかけ合い、効いた効かないと頑張ったり、先輩にかけてもらったりしたものだ。 特に、二教はみんなでよくかけ合った。一対一で左右の手首をかけ合ったり、二人で一人で左右の片方づつの手をとって、相手が参ったといっても手が叩けない状態にしてかけたり、木の短刀をつかってかけたりした(写真)。また、家では手の甲を床につけた腕立て伏せで鍛えたりもした。
特に、二教はみんなでよくかけ合った。一対一で左右の手首をかけ合ったり、二人で一人で左右の片方づつの手をとって、相手が参ったといっても手が叩けない状態にしてかけたり、木の短刀をつかってかけたりした(写真)。また、家では手の甲を床につけた腕立て伏せで鍛えたりもした。
技をかけるだけでなく、受けの取り方も大事なのである。相手に背中を見せて逃げれば痛さを回避できるが稽古の意味がなくなる。相手の力を受け止め、自分で関節を鍛えるのである。また、いつでも相手に反撃できる態勢を取ることにもなる。相手に背中を見せて受けたりすると、肘関節を決められたものだ。
関節はある程度鍛えると効かなくなるので、効かなくなってきたなと思うまで鍛錬すべきである。そのタイミングとは、仲間や先輩が二教などの関節をきめる鍛錬稽古に寄って来なくなるときである。関節が弱いうちは沢山集まってきて関節を鍛えてくれるものだ。
開祖は、関節技は相手を痛めるための稽古ではなく、そこに溜まっているカスを取り除く稽古であると言われていた。身体の節々にカスが溜まっていては血液も気も流れず、稽古が先に進まないだろう。
昔のように相手を制するためではなく、自分の関節のカスを取り除き、しっかりした骨関節をつくるためにも関節も鍛えるべきだろう。
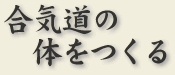

 合気道の体をつくる
合気道の体をつくる