【第102回】 手を刀として使う
合気道の技は一般に手でかけるのだから、手の働きが大事である。手は相手との間合いを取ったり、相手の"ツボ"を打ったり、押さえたり、また持たれた手で技をかけたりする。
かって本部道場の有川師範は、「手は刀のように使え」と言われ、手の使い方と用法を示して下さった。手(腕)は肩から指先までを剣としてつかわなければならないとのことである。親指を上に向けて立て、親指側が刀の峰となり、下の肘側が刃となる。切るところは手の手刀(しゅとう)となる。
手を刀のように使えという意味は、手(腕)を剣に見立てろということだけでなく、手が一本の剣のようにならなければならないということである。つまり手が折れたり、曲ったり、ゆがんだりしては駄目だということである。持たれた手がちじんだり、折れてしまうのは、ナマクラ刀と同じで良くないことになる。
また手を剣のように使うとしたら、相手に手を持たせるときでも、手は刃筋が真下に向き、峰が真上を向くようにしなければならない。正面打ちや横面打ちで打つ場合も、打つところに刃筋が直角に当たるようにしなければならない。剣でものを切るとき刃筋が通っていなければ切れないからである。また相手を打つにしろ、相手の手の打ちを捌くにしろ、手は剣の捌きのように、螺旋で捌かなければならない。直線で捌けば相手の剣(手)で切断されるし、体との連動した動きができない。
手を剣のように使うためには、はじめは意識して使わなければならないだろう。意識することによって、手に気持ちが入り、刀のようなしっかりした手ができてくるし、使えるようになる。ただ、道場の相対稽古では相手を意識するので、自分の手の状況に意識が行きにくいし、今のはよくなかったと気づいても修正するのも難しいので、自主稽古での一人稽古が必要になる。
まずは、手を剣として振る稽古がよい。稽古というのは、単純化した方がよい。「正面打ち、横面うち、突き」を繰り返す。これが出来るようになったら、「正面打ちで打ち下ろして切り上げる、次に袈裟懸けに切り下ろして同じところを袈裟で切り上げる、その次に反対側から袈裟懸けに切り下ろして切り上げる、そして手を水平の位置まで下ろし左右に切る」。これは、米(こめ)の字に手を振る稽古である。この稽古は、故有川師範(写真)が残された稽古法である。注意しなければならないのは、肩を貫いて刃筋が立つように手を返しながら使うことである。

手が剣であるわけだから、剣である手は原則的に自分の正中線上になければならない。片手取り四方投げなどは、取らせる手が数センチ、数ミリでも中心からずれると、力は全然違ってしまう。上手な人ほど手は中心を押さえる。手は正中線に集まるように使うことが肝要である。両手を使う場合は、原則的に両手の中心が正中線(通常はへそ)になる。
剣である手は、腹と常に結んでいなければならない。剣で切る場合、剣先を動かして切るのではなく、その対極にある腹や腰で切らなければならない。重い鍛錬棒を振ると分かるが、手先では振れないものである。腹、背中、腰でないと振れないものだ。例え一時的に振れても、その内に肩をこわしたり、手首を痛めてしまう。従って、手(腕)も手先を動かすのではなく腹、背中、腰を動かさなければならないことになる。
手を腹や腰の体幹で使えるようになれば、次には手に剣を持ったイメージで手を使うことである。遠い間合いから相手の気持ちを引き出したり、相手の気持ちを切り、自分の渦の中に相手を取り入れてしまうのである。手を剣のように自在に使えるようになれば、相手は、手が触る前に剣でやられたと感じ、気持ちと体勢が居ついてしまうものだ。ここまで来ないと武器取りなどできないはずである。
手はまず意識して剣になるように鍛え、次に剣として使えるように鍛え、さらに自分の手が剣になったイメージで自在に使えるようにしなければならないだろう。
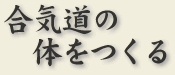

 合気道の体をつくる
合気道の体をつくる