【第330回】 天地の呼吸に合わす
合気道の目標とするところは、宇宙との一体化、いうなれば宇宙人になることだろう。合気道開祖はそういわれているが、その目標を定めても、どのような稽古をすればよいのかが難しい。それに、これがそうだろうと思ってやっても、それが正しいという保証があるわけではないので、試行錯誤を繰り返すことになる。
しかしながら、物事は人が考えているように膨大で、摩訶不思議ではなく、単純明快なものなのかもしれない。例えば、宇宙とか天地を、我々は自分たちが近づきがたく、また自分たちに関係のない外のものと考えているが、どうもそうではなくて、もっと身近なものであるようだ。
開祖は、宇宙は自分の中にあるのであって、合気道は宇宙のいとなみが自己のうちにあるのを感得するものである、といわれている。宇宙があるとすれば、天もあるし、地もあることになる。人の身の内には、天地の真理が宿されているのである。身体は黄金の釜なのである。まず、それを信じることであろう。
相対で稽古をする相手に技をかけても、なかなか思うようにいかないし、相手も納得してくれないものである。しかし、時として、うまく技がつかえることがある。技をかけた自分も驚くが、受けの相手は逃げるに逃げられず、ただ受けを取らざるを得ない状態になり、驚いたり、恐れたり、そして納得する。
それは、自分の微力な力以上の力が働いた時である。その一つが、天地の呼吸に合わせた力である。人の肉体だけからくる力には限界があるが、天地の呼吸を味方につけた力は、人力を超越したものになる。
なぜ天地の呼吸に自分の呼吸を合わせることができるかというと、開祖が、天地の呼吸と自分の呼吸は同じものであるといわれているように、それが同じだからであろう。
合気道の技は、天地の呼吸に自分の呼吸を合わせて、つかわなければならない。その要領を掴むのは、始めは難しいが、それが分かりやすい稽古法をいくつかみてみよう。
ひとつ目は、四股踏みである。息を吐きながら、重心を落とした足元に、肩の力とともに、全体重を真下におろす。息が下腹で圧縮されたところで息を入れると、地からの抗力がきて、反対側の足に伝わり、足が自然に天に上がってくる。足自体を上げたり下ろしたりしてやろうとしても、なかなか上手くいかないものである。四股を呼吸で、そして天と地の呼吸に合わせてやると、この天地の呼吸が分かりやすいと思う。
二つ目は、呼吸法である。天地の呼吸の稽古は、どの呼吸法でもできるはずだが、最も基本となる諸手取りの呼吸法がよいだろう。承知のとおり、捕りであるこちらの一本の手を、受けの相手は二本の手で取りにくるわけだから、力では2対1で負けてしまうだろう。だから、力以外のもののお世話にならなければならない。それ故、諸手取りでは、この天地の呼吸の重要性は分かりやすいはずである。十字の手足の使い方と合わせてやれば、相当な力が出るはずである。
縦に立てた手(の平)と同じ側の足を、地の呼吸に合わせ、息を吐きながら下にちょっと下ろすと、抗力が手先に伝わってくる。そこで息を吸いながら、手を今度は横に返し、反対側の足に重心を移すと、相手もついてくる。そこで、手をまた縦に返し、振り上げていくと、相手は浮き上がる。ここで、息を吐きながら、相手の首を切り下ろすように落せばよい。天地の呼吸に合った息づかいと動きができれば、不思議と相手は軽くなるものだ。
三つ目は、二教裏の小手廻しである。この技が効かないのには、いろいろな原因がある。相手が強いばかりではない。体の裏の力をつかってしまったり、手足を陰陽でつかわない、手先でやってしまう、などがあるが、天地の呼吸に合わせないで、自分勝手、つまり自分の腕力でやってしまうことにある。
この技がきまるためには、先ず自分の気持と息(吐く)を地の呼吸に合わせて前足で真下に落し、息を入れながらその力の抗力を反対側の足に移していくと、受けの相手が浮き上がってくる。そこで、後ろ足から前足に重心を移し、息を出しながら、体全体の力を手先に集め、地に落としてきめるのである。多少がんばられても、体全体の力を天地の呼吸に合わせれば、相当の力が出るはずである。
四つ目は、半座半立ちの四方投げである。持たせた手を息に合わせて、十分に地に落とすと、今度はその手が天に上がるものだ。また、天地の呼吸に合わせれば、大きな力が出るだけではなく、拍子も自由に取れる。逆に、自由に力強く動くためには、天地の呼吸に自己の呼吸を合わせてやらなければならない。
もちろん、他のすべての合気道の技も、天地の呼吸に合わせなければ、うまくできないはずだ。自分の中に天地の真理が宿っているわけだから、それをつかわせて頂けばよいのである。まずは、天地の呼吸に合わせてやってみるとよい。
武道は天地の真性に学んでいかなければならないようである。そろそろ人間の殻を脱皮しなくてはならないだろう。
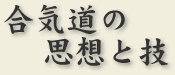
 合気道の思想と技
合気道の思想と技
